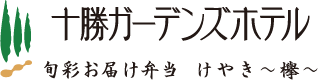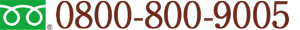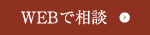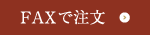七夕というと、、、7月7日を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
実は本来、七夕は旧暦(伝統的な暦)で祝っていた行事でした。
現在使っている新暦(太陽太陰暦)にすると、2025年の七夕は8月29日です。
これは近年の中でも特に遅い日付で、8月末の七夕はちょっと珍しいことのようです。
今回はそんな七夕についてご紹介いたします。
七夕はいつ始まった?
七夕はもともと中国の行事で日本には奈良時代に伝わったと言われております。
平安時代の宮中行事として
平安時代には、七夕は宮中行事として行われるようになり、
お供え物として、もも、なし、なす、うり、大豆、干し鯛、アワビなどを並べ、
貴族たちは星をながめて歌を詠み、女性たちは針に5色の糸を通して
供え物と一緒に並べ、裁縫が上手になるようにと祈ったとのこと。
また、願い事を梶の葉に書いたという記録もあり、これがその後、
短冊に願い事を書く習慣になったそうです。
江戸時代には庶民の行事にも広まる
宮廷では一年を通して、さまざまな行事が行われてきましたが、
江戸時代になると幕府がそのうちの5つを「五節句」として式日に定め、
七夕は「七夕の節句」として五節句の一つとなり、庶民の間にも広まっていったようです。
七夕の由来は?
七夕の由来といえば、「織姫と彦星」の伝説が有名ですが、その他説もございますので、
ご紹介いたします。
「織姫と彦星」
こと座のベガとわし座のアルタイルは、天の川を挟んで並び、七夕の頃、夜空でひときわ輝きます。
中国の人はいつしか、七夕を年に一度、ベガ(織姫)とアルタイル(彦星)が出会える日と考え、
「織姫と彦星」のストーリーが生まれたそうです。
日本の神事「棚機(たなばた)」
中国から七夕が伝わる前、日本ではすでに7月7日は別の行事が行われていたようで、
それが「棚機(たなばた)」「棚機津女(たなばたつめ)」と呼ばれる行事だったそうです。
秋の豊作を神様に祈るために、若い女性が選ばれ、水辺に小屋を立てて籠り、
神様に備える布を織ったそうです。これが「棚機」の行事です。
中国の宮中行事「乞巧奠(きこうでん)」
中国では古くからベガ(織姫星)は針仕事を司る星とされており、
一方、アルタイル(彦星)は農業を司る星とされてきました。
乞巧奠は、中国で7月7日の夜に行われた宮中行事であり、女性たちは織姫星に手芸や裁縫、
機織りの上達を願ったそうです。この儀式が日本に伝わり、平安時代には宮中や貴族の間に広がったそうです。
先ほど紹介した「棚機の行事」と、中国から伝わった「乞巧奠」や織姫の話がいつしか
融合していったと言われております。
七夕とはどんな行事?
短冊に願い事を書いて笹竹に吊るし、夜空に祈る
七夕は、中国の宮中行事だった「乞巧奠」が日本に伝わり、日本古来の「棚機」と融合し、
宮中や貴族の女性たちが針仕事の上達を願って、織姫と彦星に祈る行事となりました。
そのとき、笹や竹はお供え物として捧げられました。
それがいつしか宮中で、梶の葉に和歌を書き、書の上達を願う風習とも合わさり、
短冊に願い事を書いて笹竹に吊るすようになったと言われております。
日本三大七夕まつり
「仙台七夕まつり」(宮城県仙台市)、「湘南ひらつか七夕まつり」(神奈川県平塚市)、
「おりもの感謝祭 一宮七夕まつり」(愛知県一宮市)は、日本三大七夕まつりと呼ばれています。
上記の他にも、各地で様々なイベントやお祭りが行われておりますので、
お住いの地域などで七夕イベントを調べてみるのも良いかもしれません。
今回は7月7日の七夕についてご紹介いたしました。
次回は、北海道の七夕についてご紹介したいと思います。