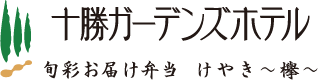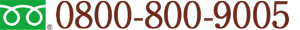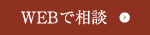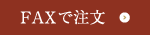昨今よく耳にする、金運が良い日とされる「一粒万倍日」などの吉日。
宝くじを購入したり、お財布を新しくしたりする方も多いのではないでしょうか。
「大安」など馴染みのある吉日だけでなく、「天赦日」「寅の日」なども浸透し始めています。
今回はそんな日本の吉日についてご紹介いたします。
吉日の歴史
古来より暦の中で、いくつもの吉日が決められてきました。
暦の中の吉日は、統治者や民衆に信じられてきており、人々の暮らしに大きな影響力を
持っていたようで、あまりにも暦の吉凶にこだわるあまり、時には弊害も出ていたようです。
お日柄を気にするのは日本人ならではの価値観かもしれません。
現在でも、結婚式・開業・地鎮祭などの建築関係など、お日柄を重視することが多く、
今では宝くじやお財布の購入に吉日を選ぶ人も少なくありません。
吉日が決まる仕組み
代表的な吉日を決める根拠は、「干支」を用いています。
日付を割り当てられた干支を元に、陰陽五行や占星術、方位学などを組み合わせて、
一定の法則にのっとり、日の吉凶は決められていきます。
吉日の種類
吉日は、それぞれによって日にちを計算され、年に1度のものから、
月に1度、2ヵ月に1度、さらには年間70日ほどあるものまで、さまざまです。
今回は現代でよく使われている代表的な吉日をご紹介します。
- 大安(たいあん):六曜のひとつの吉日で、「大いに安し」という意味があります。
大安の日は、一日中が良い日とされ、朝から晩まで吉なので、結婚式などの
一日がかりのイベントをするのに向いています。
- 一粒万倍日(いちりゅうまんばいび):「一粒のもみが、万倍もの稲穂を実らせる。」 という意味があり、「1つの行動が万倍もの結果となって帰って来る。」という意味で 使われています。
商売をはじめ、何をするにも向いている吉日とされています。月に4~7回ほどあります。
- 天赦日(てんしゃび):陰陽五行説と干支から由来しており、「すべての神様が、 人々の罪を赦(ゆる)してくれる日」と言われています。
1年の中で5∼6回しかありませんが、吉日の中で最強とも言われており、 結婚式、開業はもちろん、財布を買うなど何かを始めるのに最適な日とされています。
- 寅の日(とらのひ):寅は、毛並みが黄金色なこと、金運の神・毘沙門天が寅年の寅の日、 寅の時間に姿を見せたことなどから、金運を呼ぶと言われています。 12日に一度のペースできます。
- 天恩日(てんおんにち):日本で古く使っていた宝暦暦(ほうりゃくれき)という暦から 由来しており、「天の恩恵が、全ての人にふりそそぐ日」という意味で、結婚式や結納、 厄払い、地鎮祭など多くの慶事に最適な日と言われています。5日間続く吉日です。
- 巳の日(みのひ):「巳」は、干支の蛇のことを指します。
白蛇は財産と才能の神・弁財天の遣いと言われており、白蛇の皮をお財布に入れておくと、 金運が上がるという言い伝えもあるほどで、金運全般に良い日とされています。 12日に一度のペースできます。
- 己巳の日(つちのとみのひ):「巳の日」のさらにパワーアップした日です。
巳の日だけでも金運が良いのに、己の日が重なることで、さらに縁起が良く、 金運の大チャンスと言われています。60日に1度しか巡ってこないので、 高額の宝くじを購入したり、数年に一度のしっかりしたお財布を購入する タイミングを当てると良いかもしれません。
- 大明日(だいみょうにち):太陽が、天地をすみずみまで照らし、恵みを受ける という意味ですがすがしい吉日です。
- 母倉日(ぼそうにち):母が子を慈しむように、天が人を慈しむ日と言う意味があります。
基本的には、全てにおいて吉日なのですが、母と関係のある行事、例えば結婚や入籍など には特に縁起が良いと言われています。月に4~5日あります。
ご紹介したのは、ごく一部の吉日ですが、いかがでしたでしょうか。
吉日やお日柄を少しだけ意識して生活してみると、不安な気持ちが抑えられ、
何事にも挑戦しやすくポジティブに生活できそうですよね。